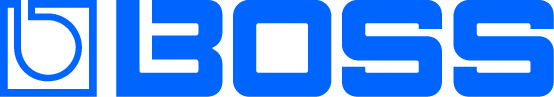ARIatHOMEは、独自の即興パフォーマンスによって、ソーシャル・メディア上で根強いファンの支持を集めてきました。ライブ配信者としての活動は、自宅のスタジオにて最長で10時間にも及ぶマラソン配信から始まります。やがてマンネリ化を避けるため、約25kg(55ポンド)もある精巧なモバイル・リグを設計し、それを使ってニューヨーク市を中心とした街中でのパフォーマンスを開始。出会ったアーティストとその場でセッションを行うようになりました。演奏する場所に関わらず、彼が愛用するBOSS RC-505mkII Loop Stationは常に演奏の大部分を締めています。
スタジオをストリートへ
クラシック音楽に囲まれたご家庭で育ったということですが、そのような音楽的背景は現在のご自身の表現にどのように活かされているのでしょうか?
兄弟姉妹全員が、子どもの頃にピアノのレッスンを受けてました。それが一番大きな影響だと思います。ただ、私自身は練習が本当に嫌いで、11歳の頃に両親が快くレッスンをやめることを許してくれたんです。でも、リビングルームには素晴らしいピアノが置いてあり、それを使って11歳以降は自然と鍵盤での即興を始めるようになりました。父はよく「Debussyみたいだね」といった褒め言葉をかけてくれました。たとえ実際にはひどい音だったとしても、そう言ってくれていたんです。
モバイル・リグのアイデアは、どのようにして思いつきましたか?
もともと即興音楽に惹かれたのは、単純に「音楽を作るのが好きだから」という理由からでした。ただ、ビートや曲を制作しようとすると、決めなければならないことがとても多くて、それが自分にとっては大きなストレスだったんです。数年前から、部屋で即興演奏を始めたのは、「少なくとも音楽を作ることができるように」と考えたからでした。決断に縛られて動けなくなるくらいなら、自由に即興をしたほうがいいと思ったんです。
ただ、それを3〜4年続けていたら、少し飽きてきてしまって。「もっと楽しくて、もっと面白く、誰かとつながれるような形にはできないか」と考えるようになりました。外が良い天気の日に、人々が外で楽しそうにしているのに、自分だけが部屋に閉じこもって音楽を作っている。そうした状況に、少し悲しさを感じることもありました。ライブ配信の世界には内向的な方が多いかもしれませんが、私はそうではないので「何とかして外に出たい」と思ったんです。
このリグを組み立てるのに、どれくらい時間がかかりましたか?
かなり長い時間がかかりました。アイデア自体は2022年にはあったのですが、最初のバージョンが完成したのは2023年の4月です。そして、それがちゃんと機能するようになったのは2023年の終わりか、もしくは2024年になってからでした。それでも、今でも時々ランダムに何かが壊れたりします。最近ではかなりスムーズに動くようになってきましたが、ステージに立つたびに「何かとんでもないことが起きるかもしれない」というリスクは常にあります。
このリグを作るにあたっては、もっと複雑な機材のセットアップを、シンプルに接続してすぐ使えるような仕組みにまとめたいと思っていました。うまく動いているときは、まさにそのとおりなのですが、時々うまく動いてくれないこともあります。私自身がストレスを感じているときほど、機材も問題を起こしやすいような気がします。なんだか、こちらの精神状態に反応しているみたいです。
「作曲はすべてルーパーで行っています。Abletonも使っていますが、それは主に楽器のパッチ・バンクとして使用しているだけです。録音はすべてRC-505mkIIを使っています」
ループの司令塔
最初にBOSS RC-505 Loop Stationを知ったきっかけは何でしたか?
Marc Rebilletのレビュー動画を見たのが始まりです。16歳のとき、NYUのサウンド・プログラムに夏のあいだ参加していたのですが、そのときルーパーが欲しかったんです。でも、なかなか満足のいくマルチ・トラック・ルーパーが見つかりませんでした。当時はReggie Wattsの演奏をよく見ていましたが、彼が使っていた小さな緑色のループ・ボックスではトラック数が足りないと感じていました。それから3年後、Marcの動画を見かけて、「ああ、これはマルチ・トラックが使えるんだ、なかなか良さそうだな」と思ったんです。それが2019年で、そのときにRC-505を購入しました。
Twitchの配信では、ルーパーをどのように取り入れていますか?
楽曲全体の構成をルーパーで行っています。Abletonも使っていますが、それはほとんど楽器のパッチバンクとして利用しているだけです。録音はすべてRC-505を使っています。そうすることで、すべてのプラグインを使うことができ、CPU負荷の高いプラグインからでも自由に音を選び出すことができます。というのも、常に音を重ね録りしているので。楽曲全体はRC-505で作り上げているんです。

「見た目も音も本当に洗練されたライブ配信というコンセプトが好きなんです」
RC-505はライブ・パフォーマンスでどのように使っていらっしゃいますか?
あらかじめ録音されたループは一切使っておりません。以前はAbletonにいくつかドラム・ループを入れていたのですが、RC-505のクロックを基準にしているので、うまく同期させることができなかったんです。メトロノームもRC-505に頼っています。時間的な同期エフェクトもそんなに多く持っているわけではなくて、MIDIクロックとAbletonのデジタル・クロックは別物なので、RC-505を中心にするほうが自分には合っていると感じています。
RC-505mkIIでは、どのようなレイヤリング技法を使っていますか?
細かい音をたくさん重ねて、曲に複雑さを加えるようにしています。オーバーダビング(重ね録り)もかなり多くやります。32小節のループに、1時間かけてひたすら音を重ねていくこともあります。音作りのアプローチとしては、ひとつの楽器で1フレーズを演奏するというよりも、小さなループをいくつか作って、そこに少しずつ音を加えていくような形です。ここに一つ、あそこに一つ、という感じで。
ボーカルのフックに関しては、まずメインのラインを録音して、そのあと左右に1本ずつ追加で録音します。そしてハーモニーも左右に録音します。外で演奏していると、「なんで同じサビを何度も録ってるの?」と不思議がられることもあるんですが、スピーカーではステレオ感があまり伝わらないので仕方がないんです。私にとって最も大切なのは、最終的なミックスの音が本当に良く聴こえることなんです。
見た目も音も洗練されたライブ配信というコンセプトがとても好きです。しばらくのあいだは、「RC-505でのミックスの完成度」に誇りを持っていました。もちろん、屋内のほうが音は圧倒的に良いです。外では難しいですからね。でも、できる限りスタジオ品質やプロフェッショナルな音に近づけることは、私にとって非常に重要です。
流れを保つということ
10時間におよぶライブ配信のなかで、まるまるアルバム1枚分の音楽を作っていますよね。そんな長時間、どうやって集中力や創造力を維持しているのですか?
集中力が切れることもあります。ただ、視聴者がいてチャットで会話できる人たちがいることが大きな助けになります。エネルギーは、そのやりとりの中から生まれるんです。チャットを読みながら演奏するというのはとても親密で素敵な体験で、長い時間観てくださる方がいることに感動しています。
もう一つのモチベーションは、長くやればやるほど、自分の演奏が上達していくという実感です。これは主に緊張と関係しています。緊張していると、どうしてもお決まりのパターンに頼ってしまいやすくて、新しさや面白みがなくなってしまうことがあるんです。ちょっと冗談めかして言っているんですが、「自分が本当にウォームアップするには4〜6時間かかる」と思っているんです(笑)。
6〜7時間を過ぎたあたりから出てくるアイデアこそが、いつも最も面白くて、最高の音楽が生まれる時間帯なんです。だからこそ、「もっと続けよう」と思えるんだと思います。長く配信すればするほど音楽が良くなると分かっているからですね。
RC-505やルーピング全般において、他に「これはユニークだ」と感じたクリエイターはいますか?
Beardymanは、おそらく史上最も技術的に優れたライブ・ルーパーだと思います。本当にインスピレーションを与えてくれる存在です。以前はRC-505を使っていたのですが、現在は自分で作ったルーピング・システムを使っていて、iPadを複数使った構成で、いろいろな画面があるんです。彼は、「ジェスチャーによる操作ができると、同時により多くのアクションが可能になる」と言っていて、それには納得がいきます。
ただ、ハードウェアの“触覚的な要素”は、自分にとっても多くのルーパーにとっても非常に重要なんです。屋外で配信しているとき、太陽の光で画面が見えにくくなるので画面に頼るのは難しいんです。ですから、私のルーピングには少なくとも何らかの触覚的な要素が常に必要になります。
歩道がステージ
最近、NAMMのBOSSブースでパフォーマンスされましたね。あの経験はいかがでしたか?
BOSSのブースは本当に素晴らしかったですし、現場にいた皆さんもとても親切でした。才能ある方々、シンガー、ラッパー、インストゥルメンタリストなど、多くの音楽仲間と出会い、交流することができました。Adrian Lylesさんとの共演もとても良い感じで、1時間くらいのあいだ、いろいろな人が次々に演奏しに来てくれて、それがとても面白かったです。
多くの演奏者が入れ替わっても、しっかりビートや構成をキープされていたのが印象的でした。
実は、外でも今そんな感じになりつつあるんです。新たなチャレンジですね。以前は、道で誰かと出会っても、その後20〜30分くらい誰とも会わない、ということが普通だったのですが、最近ではSNSの投稿を見た人たちがどんどん寄ってきてくれるようになりました。昨日は、3時間ほどずっと途切れずにそうしたセッションが続いて、本当に面白かったです。
街中で認知されるようになってきたことについて、どのように感じていますか?
すごくクールなことだと思います。多くのパフォーマーの方々は、ステージに立ちたいとか、人に観てもらいたいという強い思いを持っているように感じます。でも、私自身はそうした動機で動いているわけではないんです。もちろん、人が観てくれていたり、誰かが踊ってくれていたりするのは素敵なことです。でも、私がこれをやっている一番の理由は、「音楽を作るのが好きだから」であり、「自分が作った音楽が良い音に聴こえるのが好きだから」なんです。
人が集まり始めると、内心では「どうやってこの人だかりから逃げようか」と考えてしまうこともあります(笑)。私は、目の前の観客を楽しませること以上に、音楽自体に集中していたいタイプなんです。でも、それもきっと、これから上達していく部分だと思います。観客とのつながりが上手くなればなるほど、そういう要素ももっと楽しめるようになるでしょうし、緊張して音楽を急ぎすぎてしまうことも減ると思います。
「上手くなる前に、自分を外に出さなきゃいけない。それが僕のやったことです」
終わりなき進化
これからのビジョンや目標を教えてください。
現時点での目標は、今の活動を続けること、でも惰性にならないようにすることです。このリグを作ったのも、自分の部屋で数年間ずっと同じようなことばかりやっていて、即興のスキルは少しずつ上達していたものの、「とびきり変わったこと」には挑戦していなかった、つまり自分で作った居心地の良い場所で収まっていた。そんな実感があったからなんです。だからこそ、今やっているこの活動も、2〜3年後にまったく同じことをやっていたくはないと思っています。これからも自分を広げて、もっと面白くてクールなことを探していきたいです。
ルーピングを始めたばかりの人へのアドバイスはありますか?
上手くなる前に、とにかく外に出てみること。それが、私自身がやってきたことです。即興演奏やビート制作を「一気に上手くなりたい」と思って始めた頃、本当にひどい出来でした。自分でも、「これは人生で聴いた中でも最悪のビートだな」と思うようなものを作っていたくらいです。
新型コロナが始まったころ、即興演奏をやりたいと思っていきなり配信を始めたんです。ひどい演奏をしている自分をそのまま配信しました(笑)。始めてから1ヶ月以内に、「大学生向けのFacebookページ」に掲載されました。そのページには70万人ほどのメンバーがいて、私は運営にメッセージを送り、毎週金曜日にライブ配信する枠をもらったんです。だから即興ルーピングを始めてたった1ヶ月で、私は2〜3年かけても得られなかったであろう規模の観客、700〜1000人の大学生たちに向けてパフォーマンスすることになりました。
演奏はひどかったです。多くの方は優しく見守ってくれましたが、中には「これ、正直そんなに良くないよね」という反応もありました。それでも、やめるわけにはいきませんでした。それが上達する唯一の方法は続けることだと思ったからです。私は、「自分の音楽は、いちばんダメだったビートや曲のレベルにしかならない」と思っています。だからこそ、ひたすら挑戦を続けるしかないんです。
火の中に飛び込むような選択をされたんですね。勇気が必要だったのでは?
ええ、でもそれが一番早いやり方なんですよ。不思議なことに、屋外で演奏を始めたとき、すぐにまた下手になってしまったんです。屋外での演奏は本当に体力的にもきつくて、難しいんです。歩いている場所や人々の視線のこと、それにチャットの読み取りなんかで、気が散る要素がすごく多くて。気づいたら、作っている音楽が3年前に作っていた、あまり良くないやつみたいな音になってしまっていました。ほとんど、「この種類の音楽の作り方を、もう一度学び直さなきゃ」と思うほどでした。それでも私は、まだ配信を続けていて、正直ひどい音を流していたこともありました。でも分かっていたんです。これはやり続けるしかない。時間をかければかけるほど、絶対に上手くなるって。