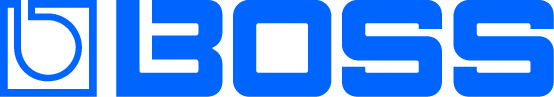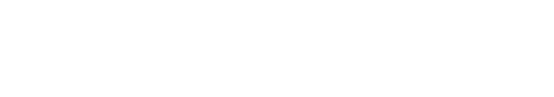1980年代初頭のハーレムの街角を思い浮かべてみてください。喧騒に包まれたニューヨークの街角で、ある音が鳴り響き、それを聴いた人々が足を止めます。素人目には、まるでパーカッションと“重機”が真っ向からぶつかったような“パン、パチン、シュー、ドシン”という音。とても原始的で、瞬時に心を惹きつける音です。勇気を出して近づいてみると、それらの音はすべて人間の喉から出ていることがわかります。ヒューマン・ビートボックスの登場です。では、時代を2021年まで早送りしましょう。BOSS RC-505mkIIのようなツールの登場によって、ループ・パフォーマンスの進化は今もなお加速し続けています。
継承される伝統
「すべての音楽、すべてのビートが口だけで作られる。はじめはどのようにして音を出しているのか理解できなかったし、到底信じられなかった」スイス出身の世界的に有名なビート・ボクサーであり、世界最大のビート・ボックス専用メディア 『Swissbeatbox』 のCEOを務めるPepouniはそう語ります。彼はアメリカの初期のビート・ボクサーたちから多大な影響を受けて、ビート・ボクサーの筆頭格へと上り詰めました。
音楽のムーブメントは、何もないところから自然発生するものではありません。地球上の文明を調べれば、何世紀にも渡ってビート・ボックスの起源が散見されます。例えば、北インドのヒンドゥスターニー(北インドのイスラム王朝の宮廷で発展した北インド古典音楽)の歌手は、タブラと呼ばれる打楽器を使ってリズムを刻みます。また、Paul Simonの「ホームレス」で一躍有名になった、ズールー族のイシカタミアと呼ばれる特徴的なビブラートを効かせた歌唱法もあります。
"人間の喉、鼻、唇は初めから強力な楽器だったのです。"
ブルースマンやジャズ・ボーカリストは、スキャット、囁き、ハミングなどを駆使して歌います。彼らの歌声は、戦後の地下の紫煙が漂うクラブの中、まるで異世界のような雰囲気を醸していました。人間の喉、鼻、唇は初めから強力な楽器だったのです。
ヒップホップの始まり
私たちが知っている現代のビート・ボックスは、1970年代後半から1980年代にかけてアメリカで台頭してきた、ヒップホップ・シーンの重要な要素として黎明期を迎えます。この熱気に満ちたサブ・カルチャーを牽引したDJ、MC、グラフィティ・アーティストとともに、ビート・ボックスはそれ自体が“アートの形態”となったのです。最初はボーカルの引き立て役という位置づけでしたが、フロントマンが即興で熱いビートを刻むパフォーマンスを行う様になると、その後、急速にビート・ボックスそのものがメイン・イベントとして注目を集めるようになります。
やがて、ビート・ボックスは猛烈なスピードで進化していきます。何千人ものアーティストたちがビート・ボックスを推し進めていったのです。彼らのミッションは、ビート・ボックスにおいて新しい分野を切り開くこと。その結果、クリック・ロールやホイッスル、ホロー・クロップなど、さまざまなテクニックが生まれました。両手を用いたギター・タッピングのルーツが長年議論されているのと同様、“最初のビート・ボクサー”についても諸説あります。
ヒップホップの歴史をよく知る人の中には、1983年、ニューヨークのラジオシティ・ミュージック・ホールにて開催された伝説的なタレント・ショーが、ビート・ボックスがブレイクするきっかけになったと言う人もいます。そのショーで、ザ・ファット・ボーイズ(Mark “Prince Markie Dee” Morales、Damon “Kool Rock-Ski” Wimbley、 Darren “The Human Beatbox” Robinson)が優勝。彼らの勝因は、Robinsonの大胆なスタイルと呼吸法によるところが大きかったようです。

"誰であろうとどこから来ようと、誰からも歓迎され、誰もが挑戦できる" -Andreas "Pepouni" Fraefel

「Buffyはたちまち人気者になったよ。」Pepouniはそう話します。「だけど、ビート・ボックスの先駆者達はまだまだ他にもたくさんいる。アメリカの歌手、Doug E. Freshは、ビート・ボックスという言葉を初めてフライヤーに載せた人物。他にも、一番最初にこのスタイルを広めた重要なアーティストとして、Rahzel、Kenny Muhammad、Biz Markieなどが挙げられる。そして、実はそこにはRolandも大いに関係しているんだ」
ミックスにおけるRolandの存在
Rolandは、なぜサブ・カルチャーの中心になったのでしょうか?それはいたって簡単で、ビート・ボックスの基本的な目的は、ヒップホップ・シーンを席巻していたドラム・マシンを模倣することだったからです。ドラム・マシンは、Afrika Bambaataaの「プラネット・ロック」からビースティ・ボーイズの「ポール・リビア」まで、あらゆる楽曲で使用されていました。ビート・ボックスとは“ドラム・マシン”を意味するスラングで、このムーブメントの名前はハードウェアに由来しているのです。
Rolandのブランド力は強力でした。1972年には、地下鉄で持ち運べるようなコンパクトなサイズに無限のパーカッションを搭載したリズム・シリーズTR-33とTR-55が発売されました。1978年には、パターンを作成・保存する機能を追加したCR-78、その2年後にはシンボリックなTR-808が登場し、ザ・ブロンクスをはじめとするビート・メイカーたちの必須アイテムとなったのです。初期のビート・ボクサーたちは、経済的な理由から声でエフェクトを模倣していましたが、その基準となったのは紛れもなくTR-808の音色でした。
"TR-808が登場し、ザ・ブロンクスをはじめとするビート・メイカーたちの必須アイテムとなったのです"
スタイルの変化
アンダーグラウンドなルーツと、ビート・ボクサーのパフォーマンスが、多くの若者の純粋な初期衝動を突き動かしたことで、ビート・ボックスは急速に普及していきました。1984年にヒットした2つの映画にビート・ボックスが登場したことからも、このムーブメントの熱狂を見て取ることができます。アメリカ・ワシントン州の俳優・声優・コメディアンであるMichael Winslow(通称:1000の音を持つ男)は、映画『ポリス・アカデミー』でビート・ボックスの魅力を世に知らしめました。
Doug E. Freshは、Stan Lathan監督の代表的なヒップホップ映画『ビート・ストリート』に、本人役で出演するほど有名に。翌年、Freshの驚異的なビート・ボックスは不朽の名曲「La Di Da Di」で注目を浴び、歴史上最も多くサンプリングされたトラックのひとつとなりました。
しかし、このメイン・ストリームの“クロス・オーバー”は諸刃の剣でした。本来、ビート・ボックスは商業的で停滞したものではなく、エッジの効いた革新的なものであり続ける必要があったのです。幸いなことに、ビート・ボックスは目新しいものではありませんでした。ビート・ボックスは鍛錬して習得される技術というよりも、パーティー芸のようなものだと思われていましたが、型破りな天才たちが次々と現れたことでそれが相殺されたのです。
1985年、元ラッパーのBiz Markieは、斬新なビート・ボックスのテクニックを次々に生み出します。インワード・ハンドクラップやヒップホップ・ダンスの先駆者としても広く知られています。彼はビート間のMCテクニックを開拓し、ビート・ボックスと歌を見事に融合させたのです。
バトルの始まり
一方でBobby McFerrinは、1988年に大ヒットした「ドント・ウォーリー ビー・ハッピー」で、オーバー・ダビングしたボーカルを用いてソフトなループ・スタイルを前面に打ち出していました。その頃、アメリカのアンダーグラウンド・シーンでは、ビート・ボックス・バトルの人気が爆発的に高まっていました。その背景にはライバル同士の地域間の対立があり、ボーカリストたちは名声をかけて“音による殴り合い”をしていたのです。戦いの勝利のカギは、より優れたパターン、トーン、メロディー、エフェクトでした。
アメリカではKenny MuhammadとRahzelが二大巨頭でしたが、その後、ビート・ボックス・バトルのスリルはすぐに世界中を席巻します。「バトル・シーンはヨーロッパでも人気が出始め、非常に面白い盛り上がりを見せた。僕がこのシーンの“一員”になりたいと思ったのは、自分が誰であろうとどこから来ようと、誰からも歓迎され、誰もが挑戦できるからなんだ」。ビート・ボックス・シーンに飛び込んだ動機を、Pepouniはそう回想しました。
"従来のスタイルのボーカルやスクラッチをビート・ボックスに変換したり、ビート、スポークン・ワード、ポエトリー・リーディングの間を行き来するアーティストが出てくるかもしれません"
進化の過程
これは核心的な真実かもしれません。伝統的な音楽ジャンルとは異なり、ビート・ボックスは新しいサウンド、アイデア、そして“血統”を歓迎しました。過去40年の間、ビート・ボックスの常識は何度も打ち破られてきたのです。従来のスタイルのボーカルやスクラッチをビート・ボックスに変換したり、ビート、スポークン・ワード、ポエトリー・リーディングの間を行き来するアーティストが出てくるかもしれません。
ビート・ボックスには、地理的にも世代的にも境界線はありません。アメリカのパイオニアたちは、世界の天才アーティストたちに認められました。「ヨーロッパで始まったビート・ボックスの黄金世代がいた。Roxorloops、ZeDe、SkilleR、Reeps One、Ball-Zee、Alem、Beardyman、Faith SFX、Hobbitがその例だね」とPepouniは言う。
2000年以降のビート・ボックスに着目すると、重大な出来事があったことがわかります。1999年、Rahzelは多大な影響力を持つアルバム『メイク・ザ・ミュージック2000』をリリースしました。このアルバムではボイス・スクラッチが初披露され、シークレット・トラックの「イフ・ユア・マザー・オンリー・ノウ」は今もなお前衛的な輝きを放ち、2004年のアテネオリンピックの開会式で、このスタイルが再び世界の舞台に登場しました。

広がり続けるネットワーク
Alex Tew(通称:A-Plus)は、2000年にビート・ボックス初のオンライン・コミュニティ 『Human Beat Box』を立ち上げました。インターネット上には議論の場や解説記事などが溢れ、これによりメキシコからマニラまで、ビート・ボクサーたちの間に交流と絆が生まれました。Pepouniは語ります。「もっと多くのイベントを開催し、新しいチャレンジや革新的なコンセプトを打ち出すことで隠れた才能を発掘、育てていきたい。僕たちの使命は、ビート・ボックスの“可能性”を世界に示すこと。Swissbeatboxはそのために2006年にスタートさせたんだ。これからエキサイティングな時代がやってくることは間違いないね」。
ネクスト・レベルのルーピング
ビート・ボックスの飛躍的な進歩を語る上で、ループ・ステーションの存在と進化は欠かすことはできません。2000年以降、ライブ中に音を重ねるテクニックは一般的なものになりました。ギタリストであり開発者でもあるLes Paulは、1953年にアメリカのテレビ番組でその原型となる技術を披露しています。いくつものメーカーがルーパーを発売しようと試みましたが、その結果は満足できるものでありませんでした。そんな中、2001年に発売された初代BOSS RC-20 Loop Stationが変革を起こしました。一見、何の変哲もないツイン・ペダル・ユニットですが、Ed SheeranやKT Tunstallなど一流アーティストの表現欲求を突き動かしたのです。また、ソロのビート・ボクサーがボイス・パーカッションを録音し、重ね合わせることを可能にした初のプロ・レベルのループ・パフォーマーでもあります。Pepouniは振り返ります。
「ループ・ステーションによって、アーティストのまったく新しい表現方法が切り開かれた。BeardymanやKid Beyondがルーパーを使ったことで、ビート・ボックスが定着したことが証明されたんだ。それはまさしく新しいチャンスだった。今ではソロのビート・ボクサーでなくても、バンドのメンバーでなくても、多くのアーティストがそのキャリアをスタートさせることができる。2013年に初めてループ・ステーション・バトルが開催されたが、これは画期的なことだった」
満ち溢れるエネルギー
BOSS RC-505MKIIは、BOSSのループ・ステーション史上最も強力なものです。しかし、それだけではありません。1980年代以降、ビート・ボックスは音楽を最も直感的に表現してきましたが、それから40年経った今、ハーレムの街角の精神は、型破りでクリエイティブなパフォーマーたちが継承しているのです。高い支持を得ているフランスのビート・ボクサー、RobinはRC-505MKIIとの出会いの衝撃をこのように話しました。


“僕たちパフォーマーにとって、RC-505MKIIの登場は人生で最高の出来事のひとつだった。このルーパーがあれば、まるで自分が生まれ変わったかのようにクリエイティブになることができるんだ" -Robin